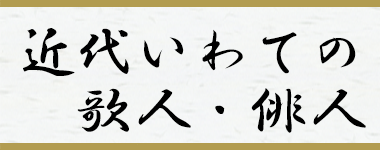現在位置: トップページ > 第2章3節 昭和初期
第2章3節 昭和初期
昭和初期の短歌
昭和2年(1927)、当時東京都・巣鴨に住んでいた菊池知勇がぬはり社を結社し、歌誌『ぬはり』を刊行します。知勇が東磐井郡渋民村(現・一関市大東町曾慶)出身だったこともあり、『ぬはり』には多くの岩手歌人が参加しました。同じころ、岩手では小田島孤舟が代表となり岩手歌集刊行会が結成され、機関誌『岩手歌集』を発行しています。
翌年の昭和3年(1928)には川合祐六らがみちのく社を結成します。機関誌『みちのく』を発行するほか個人の歌集発行にも力を入れ、下山清の歌集『わくら葉』などを発行しています。
昭和12年(1937)、小田島孤舟は関登久也(せき とくや)らと第2次岩手歌人協会を結成します。これは大正12年に結成された岩手歌人協会の後続にあたるもので、機関誌『岩手歌人』を昭和19年(1944)までに16冊発行します。同年には、西塔幸子の遺稿歌集『山峡』が出版されました。
終戦翌年の昭和21年(1946)、巽聖歌(たつみ せいか)が沼宮内で新樹社を結社し、戦後の青少年を文学運動によって安定させるとともに、詩歌文芸の後進の育成に努めました。
下山清(しもやま きよし)

下山清
[『歌集 わくら葉』より]
下山清は沼宮内小学校4年生の時に脳膜炎を患い、片目の視力と聴力を失います。残る一方の目も近視が強く、書物をかなり近づけないと見えないほどだったようです。そのため小学校は途中で除籍されてしまいますが、学力はとびぬけて優秀で『万葉集』などをそらんじるほどだったと言います。
実家の継母とうまくいかず知人を頼り放浪の生活を続けますが、その傍ら小田島孤舟や関登久也と交遊し小原節三とは短歌創作の意義について論戦を交わすなど、苛酷な日々の中で短歌を心のよりどころとして生きていたことが伺えます。清の短歌について、親友である作家の森荘已池は「芸術的に純粋で格調の高い作品」と述べています。発表した歌集はみちのく社から発行された『わくら葉』のみですが、発行の辞には「薄幸の天才歌人」としつつも「作者個人の運命をハンディキャップとして考慮せよと要求するのでは断じてなく、且(かつ)もっとも不要なことである」と清の才能を評価する言葉が残されています。
巽聖歌(たつみ せいか)

『新樹 創刊号』
[当館所蔵]
巽聖歌は、児童文学や童謡詩を創作する一方で短歌創作にも力を入れていました。北原白秋に師事した聖歌は、歌集こそ発行しませんでしたが、白秋主宰の短歌雑誌『多磨』などに多くの短歌を寄稿しています。その作風は、師である白秋の風韻を継ぐ一方で、知的な抽象表現の方法を取り込み新風を切り開いていこうとした跡が見て取れます。また、聖歌自身の人間味が感じられるような親しみのある温かさも特徴のひとつです。
聖歌は昭和21年(1946)に疎開先の沼宮内で詩歌雑誌『新樹』を創刊します。巻頭に記された「新樹は、そういうわたくしを中心として、集ってきた若い元気な人達の集りである。(中略)わたくしは正しく伝えようとしている。日本詩歌万代のためである」という言葉から、詩歌文芸の後進を育てようという聖歌の意気込みが感じられます。
西塔幸子(さいとう こうこ)

西塔幸子
[『山峡』より]
西塔幸子は明治33年(1900)、紫波郡不動村(現・矢巾町白沢地区)の大村家に生まれました。大正8年(1919)に岩手師範学校を卒業して教師となると、初任地の久慈尋常高等小学校を振出しに、現在の洋野町や宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村など県内各地の小学校で勤務します。
夫・西塔庄太郎の酒乱や、凶作に喘ぐ貧しい地方での暮らしなど、幸子の生活は決して華やかなものではありませんでした。しかし「作歌の多かったのは生活が安易で暇の比較的多かった時ではなく、反(かえ)ってその反対の場合のやうです」と幸子自身が語るように、厳しい中でも生活に向き合い、実直に生きようという信念が歌作の原動力となりました。
昭和11年(1936)5月、急性関節リウマチを発病しながらも四男を出産しますが、同年6月には肺炎を併発してしまいます。幸子は7人の子どもと2千余りの歌を遺し、36歳の若さで亡くなりました。
『山峡(やまかい)』

『山峡』
[当館所蔵]
西塔幸子の死から1年余りが過ぎた昭和12年(1937)9月、幸子のはじめての作品集『山峡』が発行されます。幸子は生前多くの短歌を作りながらも、歌集を発行したことがありませんでした。病床の幸子は、弟に「死後歌集の出版を頼む」と言葉を遺しており、歌集は幸子の弟である大村次信によって発行されました。
幸子の短歌について、次信は「姉の歌は苦しき生活の中からうめき出されたものであり、筆先の歌ではない」とした上で「私の姉は不幸の反面のみ見る性ではなかった。むしろ不遇な生活の中に幸福を見出せるだけ見出した姉である」と述べています。
貧しさに喘ぐ地方での生活や家庭苦のなかでも、ひたむきに前を見つめ、己の生涯を生き抜いた幸子の短歌は、時代を経た今もなお私たちの心を打ちます。
昭和初期の俳句
昭和に入ると、岩手の俳壇は大正から引き続き『石楠』系の俳句が主流を占めていました。
しかし、そこに盛岡出身の山口青邨(やまぐち せいそん)が『ホトトギス』に華々しく登場します。昭和5年に青邨と宮野(みやの)小提灯(こちょうちん)による盛岡発の『ホトトギス』系の俳句雑誌『夏草(なつくさ)』が創刊されると、岩手の俳壇は一気に『ホトトギス』系一色に塗りつぶされていきました。『夏草』は昭和15年に発行所を東京に移します。青邨は『夏草』を主宰する傍ら、新聞・雑誌で選者としても活躍し多くの俳人を育てました。
昭和4年には『岩手俳句集』が出版されました。その当時の、明治・大正・昭和の県内の俳人が総覧できる内容となっています。
山口青邨(やまぐち せいそん)

山口青邨
[写真提供:盛岡市先人記念館]
明治25年(1892)、盛岡生まれの俳人で鉱山学者。本名は吉郎。盛岡中学校(現・盛岡第一高等学校)、第二高等学校(現・東北大学)と進み、東京帝国大学工学部を卒業。後に東京帝国大学教授を務め、昭和28年(1953)には東京大学名誉教授となりました。
青邨は、大正7年(1918)から『ホトトギス』を読み始め句作を思いたちます。大正11年(1922)に東大に俳句会をつくり、翌年に正岡子規の弟子・高浜虚子に師事します。虚子は子規の写生の手法を受け継ぎ自ら提唱した花鳥諷詠(かちょうふうえい)(自然界と人間界の現象をそのまま客観的に歌い上げること)を俳句の理念としましたが、青邨は、客観的な写生や花鳥諷詠だけではなく主観も大事にしました。どちらか一方に偏るのではなく、その調和を重んじました。
青邨は、俳人の育成など俳句の世界に大きな足跡を遺し、昭和63年(1988)に亡くなりました。北上市の日本現代詩歌文学館の敷地内には、青邨が東京杉並区で過ごした自宅が移築復元されています。
宮野小提灯(みやの こちょうちん)

宮野小提灯
[写真提供:盛岡市先人記念館]
明治28年(1895)盛岡生まれの俳人。本名は藤吉。盛岡市下橋高等小学校を卒業し、家業の米穀商を継ぎます。15歳の頃、お盆に軒下につるされている行燈に書かれた俳句に魅せられ句作を始めたと述べています。
大正3年、高浜虚子に師事しようと『ホトトギス』に投句します。昭和5年(1930)には、山口青邨が選者、小提灯が編集・発行者となり俳句雑誌『夏草』を創刊しました。
小提灯は、生涯を庶民の俳人として生き、地方色の濃い、都会派風の俳句では味わえない趣のある句を多く残しました。そして、その土地に生活している者でなければ作れないような、土着の視点で句作を続けました。
昭和49年(1974)に、心不全のため78歳の生涯を閉じました。盛岡城跡公園には、小提灯の句碑が建立されています。
俳句雑誌『夏草』
山口青邨が主宰した俳句雑誌です。『夏草』はのちに全国でも有数の俳句雑誌となりましたが、始まりは盛岡で発行された小冊子でした。
宮野小提灯が『ホトトギス』に投句していると、俳句も文章もずば抜けた人物がいることに気付きます。その人物が、同じ盛岡出身の青邨でした。
昭和4年の夏に、ふたりは盛岡で初めて出会います。家業の米穀店を営む小提灯は34歳、東京帝国大学工学部助教授の青邨は37歳でした。この時、二人は県内の『ホトトギス』系の俳人を集めて雑誌を出そうと意気投合します。
昭和5年、東京在住の青邨を選者とし、小提灯の編集・発行により俳句雑誌『夏草』が盛岡で創刊されました。昭和15年には発行所を東京に移し、青邨は主宰となります。
青邨が亡くなった後の平成3年(1991)5月通算650号をもって終刊となりました。